昨夜、『魂の帰郷』は、音楽的な意味ではイマイチだった、と書きましたが、レベルとしては非常に高いものだったというのは、言わせていただきたいと思います。ひとりひとりの音楽家としての力量も、ありかたも、このプロジェクトへの向い方も、互いに音楽で全身全霊で会話するところも、素晴らしかったのです。
ただ、わたしの中で、どうしても不納得だったのは、映画全体に流れていたテーマだったのだと思います。それは、、、ジャズ文化のルーツをアフリカに求め,そこに『帰郷=帰る場所』を求めようとした姿勢にあった、ということです。しかし、わたしの見解では、アフリカとアメリカは違う文化である、ということです。
確かにアメリカはアフリカ文化の影響を強く受けた国です。それは、何千万ものアフリカ人が強制的に連れて行かれた土地だからです。世界は、植民地時代以降多大な影響をアフリカから受けていますが、特に、奴隷の数の多かったアメリカ大陸はそれが顕著だったのです。
この映画は、アフリカを起源とするジャズと西欧の影響も受けているアフリカポップの融合、というものが目指されていたのですが、これは「ジャズ=アフリカ起源」という狭い考え方でアプローチすると非常に難しい課題であることが明らかになった映画だった、とわたしは考えたのです。
わたしの古くからの友人に、マライア・キャリーのマネージャーを長年していた女性がいます。マライアは白人と黒人の混血ですが、この女性は、いわゆる黒人でした。彼女のちいさい時からの願いは、「mother land」母なる祖国であるアフリカにいつか戻って自分のルーツを確かめることでした。そして、ある日、休みをとり、とうとう行きました。ひと月ほどして戻ってきた彼女は、わたしに静かに言いました。
「わたしはアメリカ人だ。アフリカ人ではない。それがハッキリとわかった旅だった。衝撃だったけれど、それがわかっただけでもよしとしたい。」
多くのアメリカの黒人は、アフリカにこころのよりどころを求めます。なぜなら、アメリカで何百年という間、ものすごい差別と虐殺と虐待を受けているからです。そしてそれは、残念ながら現在でも続いているからです。この友人の女性もそうですが、アメリカの黒人女性は、黒人というだけで結婚相手をみつけるのが容易ではありません。白人からも黒人からもアジア人からも差別されるからです。それは、非常に複雑で切実で悲しい問題です。今回、黒人の大統領が生まれたのは、アメリカを肌で知らないひとたちの想像をはるかに越えた奇跡だったのです。だから、アメリカの黒人達は、自分たちを認め、自分たちの肌の色をそのまま受け入れてくれ、自分たちの安心できる場所をどこかに求めたのです。当然のことなのです。それがアフリカだったのです。
しかし、アフリカに故郷と魂のよりどころをいくら求めても、彼らは、アフリカ人ではないのです。その現実を、わたしの友人は、ハッキリと知ったのでした。60〜70年代にアメリカ黒人の間でアフリカ回帰が流行し、多くのアメリカ黒人がアフリカに戻ったのですが、ほとんどが馴染めずアフリカで病気になったり衝突したり、戻ったという過去の話しもあります。
実は、わたしも同じような経験をしてきました。わたしは幼い頃から海外と遭遇しています。そして、長い間アメリカを中心に日本以外のところで住んできました。けれど、どこにいても自分を「日本人」として認識し、日本をこころのよりどころとしていました。しかし、今回約8年前に日本に戻ってきて知ったのです。わたしは、いわゆる「日本人ではない」。それは、衝撃でした。わたしには、日本にいる「一般的日本人」の心情が理解できなかったのです。
なぜ、このひとはこっちに行きたいと思っているのに、そう言わないのか。なぜ、このひとはこの商品のことをさっぱり知らないのに、知っているふりをするのか。なぜ、このひとはこころの底で男を信頼していないのに、まるで男がいないと生きて行けないような言動をとるのか。なぜ、この国はこんなに不便なのに、みんな便利便利というのか。なぜ、この国のひとたちは、北朝鮮のような、政治的にも軍事的にもどれほどにもならない弱小国のことを異常に怖がるのか。なぜ、この国では「常識」という言葉がこれだけ多く使われるのか。そして、それがまるでひとつしかないような幻想を抱いて疑わないのか。そのくせ、なぜこのひとたちは海外にに認められることをこんなに望み、歓ぶのか。そして、なぜこの国のひとたちは、これらのことを「当然」として受け止めているのか・・・。
全く分りませんでした。そして、テレビに出てくる人たちも誰が誰だか分らなかったですし、電車の中でもクラスでもどこでも、アジア人の顔を長い間見慣れていなかったわたしにはみな同じ顔に見えて、ひとの顔を覚えるのが一苦労でした。髪を金色に染めているひとを見るたびに白人と思い込み、振り返ったらアジア人の顔でのけぞるほど驚く、というのを長い間繰り返していました。なので、一生懸命日本の歴史や社会学の本を読みあさりました。テレビも猛烈な勢いで(笑)見ました。電車に乗っても、道を歩いても、とにかくひとを観察しました。しかし、その時点で、もう、わたしは日本人ではなかったのです。
だから、アフリカに行った黒人の友人が言った意味が、本当によく分るのです。彼女にはアフリカ人が「分らなかった」のです。人間は、自分が共鳴し、意識を共有していると感じられる集団にたいして「ここに属している」と感じるものです。わたしも彼女も信じていた「祖国」は違っていた、ということになります。
これと同じように、ジャズは、アフリカを起源にはしているけれど、アフリカではすでにもうないのです。確かに、似ているところもあります。確かに、遺伝子はあります。確かに、祖先はそうだったかも知れません。けれど「違うもの」なのです。わたしが数十年の間に経験したことを、ジャズは数百年かけてしているのですから、全く異質なのです。
この映画は融合と回帰を目指しながら、結局は違いが明らかになったものだとわたしは感じたのです。そして、その非現実を現実として妄想したところに、音楽的な失敗があったと感じたのです。
しかし、だからといってそこに希望がない、というわけではないとわたしは考えます。最初から「違うものだ」と認識して向かい合えば、そこから新たなるものが生まれる可能性がおおいにあると思うのです。
アフリカポップとジャズは、似て非なるものである、というところから出発していれば、もっと自由で、もっとクリエイティブで、もっと違う新しい次元の音楽が生まれたのではないか・・・・共通点やルーツを探すところに重点を置いてしまったから,残念ながら幅の狭いものとなってしまった、と。しかしこれは、ユッスーの求めていたものではなく、きっとフランス人のプロデューサ−の犯したミスだったのだろう、と感じました。安易に「ジャズ=アフリカ」と考えるのは、どうしても当事者以外だからです。それに、ユッスーは、NYの若い歌手が非常にNY的なインプロをやったときに反応し、ハーモニカプレーヤーが自分の世界観を全面的に出したときに目を輝かせていました。ユッスー自身は、異質なるものを両腕を広げて受け入れる度量のある素晴らしいひとりのアーティストなのだ、と改めて感じました。ただ、同時に、アメリカの黒人が抱える苦しみは、ユッスーにはあまり分らないのだな、とも。
それが、わたしの印象でした。そして、なぜ、オバマ大統領が素晴らしいかというと、アジア、ハワイ、アメリカで時間を過ごし、Kansas州のまったくのアメリカ白人の母親と、ケニアのまったくのアフリカ黒人の父親という、極端に違う背景をしょって成長したことにより、現実として「ひとはみな違う」という認識をしているからだと思うのです。「違う」ということを認識してこそ初めて人間は「対話」をすることができるからです。
それを深く考え、認識し、そこから立脚した世界観を持っているのが、実は、日本では今回わたしが遭遇した南直哉さんという和尚さんではないか、と思っているのです。ま、そこまで触れると長くなっちゃいますから、ここまでにしておきます(笑)。とりあえずわたしは、これからも自分の音楽と向き合って行こう!と思ったところです。そして個人的には、自分がいわゆる「日本人」ではない、と認識してから肩の力も抜けましたし、わたしには祖国なんてどこにもない、と分ってから断然幸せな日々です。
けれど、この映画、必見です。今更言っても信じてもらえないかも知れませんが、完璧でないからといって素晴らしくない、ということではないのです。上に書いてきたことはアメリカとアフリカと深く関わってきた、祖国を持たないわたしのような人間の言うことです。奴隷の歴史とそれがひとに与える影響を知るだけでも、多大な力がある映画だと思います。映像もとても美しいです。ぜひぜひ、お時間を「作って」観ていただきたいと願います。








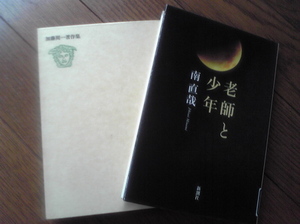




最近のコメント